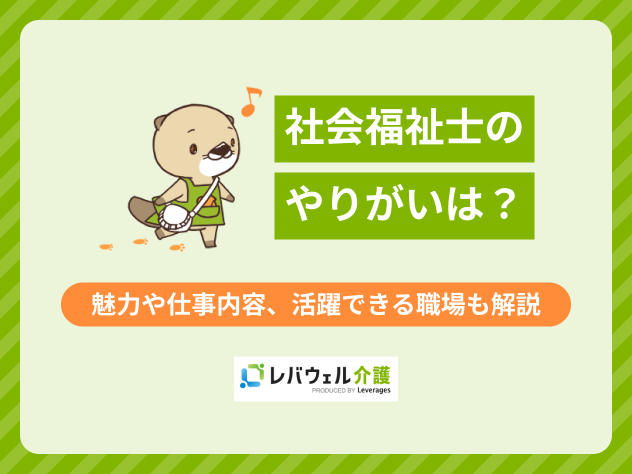
この記事のまとめ
- 社会福祉士とは、相談・援助・調整業務などを行い利用者さんを支援する仕事
- 利用者さんからの感謝や地域課題の解決などが社会福祉士のやりがい
- やりがいを感じながら長く働くには、上位資格の取得や独立する方法がある
「社会福祉士のやりがいや魅力とは?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。社会福祉士は、利用者さんの相談に対して助言や支援などを行うため、直接感謝されたり、地域課題の解決につなげたりすることにやりがいを感じられる仕事です。この記事では、社会福祉士のやりがいや魅力を紹介。社会福祉士の仕事内容や勤務する職場の種類、平均年収についても解説します。やりがいを感じながら長く働く方法も説明していますので、ぜひご覧ください。
社会福祉士とは
社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉法」に基づく国家資格である「社会福祉士」を取得している人のことです。無資格でも相談業務を行える場合がありますが、社会福祉士と名乗るには資格が必須となります。
社会福祉士は身体的、精神的、経済的など、さまざまな問題を抱える方の課題を解決する専門職です。福祉や医療、教育機関など多様な分野で、支援が必要な方の相談を受け、支援計画の立案や助言を行います。
出典
e-GOV法令検索「社会福祉士及び介護福祉法」(2025年3月18日)
内定後まで安心サポート
▼関連記事
「社会福祉士はやめとけ」と言われる理由は?向いている人やメリットを解説
社会福祉士及び介護福祉士法とは?何が書いてあるのかわかりやすく解説!
社会福祉士のやりがいや魅力
社会福祉士は、「利用者さんやご家族から感謝される」「地域課題を解決に導ける」「チームで一体となって支援できる」など、さまざまなやりがいや魅力がある仕事です。ここでは、社会福祉士のやりがいや魅力を説明します。
利用者さんやご家族から感謝される
社会福祉士は、相談支援を通して利用者さんやそのご家族から感謝される機会が多い仕事です。利用者さんは、生活するうえでの困りごとがあったり、今後の生き方に強い不安を抱いていたりする方も少なくありません。社会福祉士が親身になって状況をヒアリングし、適切なサポートを提供することで、「ありがとう」と感謝されることがあるでしょう。
地域課題を解決に導ける
社会福祉士のやりがいの一つが、地域の課題を解決できることです。社会福祉士が関わる問題の背景には、少子高齢化や介護人材不足、核家族化などの社会情勢があります。社会福祉士は、そうした背景から引き起こされる老老介護の問題や児童虐待などの相談を受け、解決を目指すのが仕事です。また、地域の社会参加の場が健全に機能するように支援を行うので、持続可能な社会作りに貢献できていると実感できるでしょう。
チームで一体となって支援できる
チームで一体となって利用者さんを支援できるのも、社会福祉士のやりがいといえます。社会福祉士は医師や看護師、保健師など、多様な職種と関わる機会の多い職種です。1人では困難な課題をチームで解決できた際にやりがいや達成感を得られるでしょう。
専門知識やコミュニケーション能力を活かして働ける
前述のとおり、社会福祉士は、利用者さんが抱える身体面・経済面・社会面の問題を解決をすることが仕事のため、高度で幅広い専門知識やスキルが求められます。たとえば、福祉全般の知識をはじめ、法律や心理学などが必要です。また、相談者の状況を正しく把握したり、他職種と円滑に連携したりするために、コミュニケーション能力が必須といえます。特に専門的な内容は習得が難しいからこそ、自身が持つ知識や能力を活かして働くことでやりがいを感じられるはずです。
人材を育てる経験ができる
社会福祉士として、ある程度経験を積むと、人材育成に携わる機会もあるでしょう。社会福祉士として相談援助の実務経験が10年以上ある方は、日本医療ソーシャルワーカー協会の推薦を得たのちに研修や説明会に参加することで、スーパーバイザー第4号(2)として登録申請することも可能です。
スーパーバイザーは、経験の浅い社会福祉士と個人またはグループ単位で契約を結び、所定の課題を通して指導・助言を行います。スーパーバイザーの役割は、経験豊富な社会福祉士が直接的なアドバイスすることによって、経験の浅い社会福祉士の専門性や実践能力を高めることです。スーパーバイザーを目指せば、自分の知識を活かして経験の浅い社会福祉士を育成できる喜びを感じられるでしょう。
出典
認定社会福祉士認証・認定機構「スーパーバイザー登録について」(2025年3月18日)
幅広い分野で活躍できる
社会福祉士が扱う分野は、高齢者福祉や障がい者福祉、医療、教育など、幅広いのが特徴です。社会福祉士の知識や技術を求めている職場は多岐にわたるため、活躍の場も幅広いといえます。社会福祉士を目指す方のなかには、活躍できるフィールドの広さや、キャリアの選択肢の多さに魅力を感じる方もいるかもしれません。
社会的需要が高く将来性がある
日本における高齢者の人口は増え続けているため、社会福祉士は需要が高い仕事といえるでしょう。厚生労働省の「我が国の人口について」によると、2040年には全人口の約35%を65歳以上が占めると予測されています。さらに、2070年の高齢化率は39%の水準に達する見込みです。
また、公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「社会福祉士就労状況調査結果(p.9)」の2020年度の調査によると、社会福祉士の勤務先の39.3%が高齢者福祉関係の施設。高齢化率の上昇により、高齢者福祉関係の施設は今後も増加が見込まれるので、社会福祉士が活躍できる職場は増えていくでしょう。
出典
厚生労働省「我が国の人口について」(2025年3月18日)
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「社会福祉士就労状況調査結果」(2025年3月18日)
自身の成長を実感できる
社会福祉士が扱う案件には、児童虐待や生活保護の受給拒否など、問題解決が難しい困難事例も少なくありません。利用者さんやご家族によっては、アルコール依存や精神障がいなどから冷静に話ができる状態ではなかったり、行政への不信感から居留守により支援を拒否してしまったりするので、思うように支援ができないこともあります。しかし、はじめは高い壁に感じた困難事例も、知識や経験の積み上げにより、解決できるようになってくると自らの成長を実感できるでしょう。
社会福祉士の仕事内容
社会福祉士の仕事内容は、「相談業務」「援助業務」「連携・調整業務」「管理業務」「情報提供業務」「介護業務」の6つがあります。ここでは、それぞれの仕事内容を詳しくご紹介するので、介護福祉士に興味のある方はご覧ください。
相談業務
社会福祉士の仕事内容の一つが相談業務です。社会福祉士は、サービスの利用者さんが自立した生活を送るうえでの相談に乗るのが役割。幅広い年代や家庭環境、性別の方に対し、相談者の生活環境や背景を踏まえて真摯に対応します。
援助業務
社会福祉士としての専門知識をもとに、助言や援助を行うのも仕事の一つです。社会福祉士は、相談者一人ひとりに合わせた支援計画を作成し、実行します。状況によっては相談者さんの自宅に訪問し、定期的な観察や評価を行うこともあるでしょう。
連携・調整業務
社会福祉士の仕事には、関係各所との連携・調整業務も挙げられます。社会福祉士は関連する医療機関や福祉施設、教育機関、行政など、勤務する職場に応じた関係機関と連携・調整するのが仕事です。地域住民やボランティア、看護師、医師、保健師、スクールカウンセラーなどと協力して円滑に業務を進めます。
管理業務
サービスを利用する際の手続きを円滑に行うための管理業務も、社会福祉士の仕事です。社会福祉士は、相談内容の記録を行ったり福祉サービス利用後にサービスが利用者さんに合っているかを確認したりします。利用者さんに合わないサービスの場合は、支援計画を改良することもあるでしょう。
情報提供業務
社会福祉士は、利用者さんに問題解決の糸口となる情報を分かりやすく伝える業務も含まれます。情報を正確に伝えるために、関係機関と連絡を取ったり、介護や児童福祉、法律など幅広い知識を身につけたりすることが必要です。豊富な選択肢から利用者さんが主体的に選択できるように、正確な情報を伝えるよう努めなくてはなりません。
介護業務
介護施設や障害者支援施設で働く場合は、社会福祉士が介護職を兼任する場合もあるでしょう。その場合は、社会福祉士の業務と並行して、食事介助や入浴介助などの介護業務を行います。職場によっては、社会福祉士が清掃や洗濯などの日常生活支援を行う場合があります。
社会福祉士が働く職場の種類
社会福祉士が働く職場にはいくつかの種類があります。ここでは、社会福祉士の職場として、を7つ紹介するので、参考にしてみてください。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、利用者さんが在宅に復帰できるよう医療的なケアやリハビリを行う施設です。介護老人保健施設で社会福祉士は、支援相談員として働きます。社会福祉士は、利用者さんが介護老人保健施設に入所する際の契約や施設での生活のアドバイス、退所手続きなど、幅広くサポートするのが役割です。
▼関連記事
介護老人保健施設で働く職種とは?医療や福祉それぞれの仕事内容を解説
地域包括支援センター
地域包括支援センターは福祉だけでなく、医療や保健などを包括的に支援する機関です。社会福祉士の仕事は、介護予防や相談、詐欺被害から守るための支援など、さまざまな内容があります。なお、地域包括支援センターは、社会福祉士の配置が必須です。
医療機関
病院の病棟やクリニックといった医療機関も、社会福祉士が勤務する職場の一つです。社会福祉士は医療ソーシャルワーカーと呼ばれます。社会福祉士は患者さんやご家族からの相談に乗ったり、利用できる医療費の補助制度や公的な窓口を案内したりするのが仕事です。
出典
公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会「医療ソーシャルワーカーについて」(2025年3月18日)
福祉事務所
地方自治体が運営する福祉事務所は、福祉業界全体の問題解決を目指す機関。各都道府県に設置されており、勤務には公務員試験への合格が必要です。福祉事務所において、社会福祉士はケースワーカーとして働きます。福祉事務所での社会福祉士の主な仕事は、地域の相談窓口として介護を必要とする方や障がいのある方、生活困窮者、児童などに対してヒアリングや支援をすることです。
社会福祉協議会
社会福祉協議会は、非営利で社会福祉活動を行う民間の組織です。社会福祉士は、医療機関や法律、行政分野の担当者と協力し、相談者をサポート。社会福祉士は、相談者の「認知症の家族と生活を続けるのが難しい」「病気になったが、入院費が払えない」など、生活に関するさまざまな悩みにアドバイスしたり、支援計画を策定したりします。
障害者支援施設
障害者支援施設は、知的障がいや精神障がい、身体障がいといった障がいのある方に対して、相談業務や支援を行う施設です。社会福祉士は、相談者が自立した生活を送るための相談対応・助言・支援を行います。相談者の障がい特性を考慮した個別の支援計画の作成や、職業訓練による就労支援なども社会福祉士の業務の一つです。
児童福祉施設
国や都道府県が運営する児童福祉施設の目的は、妊産婦や児童の福祉を支えることです。社会福祉士は、助産施設や保育所など、児童福祉法で定められている各施設で働きます。児童福祉施設での社会福祉士の仕事は、主に支援を求める児童や保護者への相談対応です。
出典
e-Gov 法令検索「児童福祉法」(2025年3月18日)
学校
学校での社会福祉士の仕事は小学校や中学校、高等学校などの生徒を対象に、いじめや虐待、生活の悩みなどの問題に対応すること。心理面だけでなく、学校や家庭の環境を改善するなど、周辺環境へのアプローチをするのが特徴です。社会福祉士はスクールソーシャルワーカーと呼ばれます。
社会福祉士の平均年収
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によれば、介護職員として働く社会福祉士の平均給与額は35万120円です。職業情報提供サイト(job tag)によれば、社会福祉士を含む福祉ソーシャルワーカーの平均年収は、425.8万円でした。
一方、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によれば、国内の労働者全体の平均給与額は、年間460万円です。国内の労働者全体の平均給与額は社会福祉士を含む福祉ソーシャルワーカーの平均年収より30万円ほど高いことが分かります。
そのため、人によっては社会福祉士の給与や年収が少なく感じるかもしれません。なお、職種や職場によって給与額は異なるため、年収の水準はあくまで目安です。
出典
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年3月18日)
職業情報提供サイト(job tag)「福祉ソーシャルワーカー」(2025年3月18日)
国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」(2025年3月18日)
社会福祉士に向いている人
社会福祉に向いている人には、以下のような人が挙げられるでしょう。
- コミュニケーション能力が高い人
- 協調性がある人
- 勉強が好き、または勉強し続けられる人
社会福祉士は、コミュニケーション能力が高い方に向いています。社会福祉士は相談者の状況や感情、価値観を、言葉からだけではなく表情や仕草など非言語的な部分からも汲み取る必要があるためです。
また、協調性がある人も社会福祉士の適性があるといえます。多くの職種や関係機関とのやり取りが発生するため、チームプレーが得意な人にも向いているでしょう。加えて、勉強が好きな人、勉強し続けられる人も社会福祉士に向いています。社会福祉士は必要な知識が幅広いうえ、関連制度の改定などが頻繁なため、常に最新情報をインプットする姿勢が欠かせません。
▼関連記事
社会福祉士に向いている人とは?向いていない人の特徴や仕事内容も解説
社会福祉士になるための方法
社会福祉士を名乗って仕事をするには、社会福祉士の資格を取得する必要があります。ここでは、国家資格である社会福祉士の取得方法や試験概要、合格率について解説します。
社会福祉士資格の取得方法
社会福祉士を名乗って働くには、社会福祉士の資格を取得する必要があります。相談援助業務を行うのに必ずしも社会福祉士の資格は必須ではないものの、資格を取得すると就職に有利に働くほか、専門知識が身につくため周囲からの信頼性が高まるでしょう。
社会福祉士の資格を取得するには、養成施設や福祉系の短大、または大学で所定のカリキュラムを履修して受験資格を得る必要があります。実務経験を積んだのちに養成施設でカリキュラムを履修する方法でも、受験資格を得ることが可能です。試験合格後は、必要書類を提出して登録申請すると社会福祉士の資格を取得できます。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]受験資格」(2025年3月18日)
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[資格登録]新規登録の申請手続き」(2025年3月18日)
社会福祉士の試験概要と合格率
社会福祉士の試験は年1回です。試験は選択式の筆記試験で合格基準は総得点の60%以上となっており、合格点は試験のその年の難易度によって補正されます。厚生労働省の「第37回社会福祉士国家試験合格発表」によると、2025年2月に行われた社会福祉士国家試験の合格率はで56.3%です。また、厚生労働省の「社会福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」によると、過去の社会福祉士の合格率は30%以下で推移していました。
このことから、社会福祉士試験の難易度は比較的高いといえるでしょう。
出典
公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]試験概要」(2025年3月18日)
厚生労働省「第37回社会福祉士国家試験合格発表」(2025年3月18日)
▼関連記事
社会福祉士試験の難易度は?合格率や試験内容、効果的な学習方法を解説
社会福祉士がやりがいを感じながら長く働く方法
社会福祉士は、キャリアアップしたり活動の幅を広げたりすることで、やりがいを感じられる仕事です。ここでは、社会福祉士がやりがいを感じながら長く働く方法として、「社会福祉士の上位資格を取得する」「成年後見人として活動する」「開業して社会福祉士事務所を経営する」の3つを説明します。
社会福祉士の上位資格を取得する
社会福祉士としてキャリアアップするには、認定社会福祉士や認定上級社会福祉士を目指す道があります。すでに社会福祉士の資格を取得している方は、ケアマネジャーや介護福祉士、精神保健福祉士を取得し、ダブルライセンスで活躍を目指すのも良いでしょう。
出典
日本社会福祉士会「認定社会福祉士制度とは」(2025年3月18日)
成年後見人として活動する
社会福祉士は知識や経験を活かして、成年後見人として活動することもできます。成年後見人制度とは、正常な判断が難しい場合、財産上の不利益を被らないために、本人に代わって財産の保護を行う仕組みです。成年後見人になるには、日本社会福祉会に登録し、成年後見人養成研修を受講したうえで、権利擁護センターの「成年後見人等候補者名簿」に登録します。成年後見人として認知症や知的障がい、精神障がいのある方の財産管理や福祉サービスの契約締結を行うなかで、ご本人の意思を代弁できるやりがいを得られるはずです。
出典
厚生労働省「成年後見はやわかり」(2025年3月18日)
開業して社会福祉士事務所を経営する
社会福祉士は、「社会福祉士が働く職場の種類」でご紹介した職場に勤務するだけでなく、独立して社会福祉士事務所を開業する選択肢もあります。開業するには、日本社会福祉士会への事業の届け出や研修を受けるなどの必要条件を満たしたうえで、名簿登録を行ってください。独立を視野に入れている方は、必要な準備を進めておきましょう。
社会福祉士のやりがいに関するよくある質問
ここでは、社会福祉士のやりがいに関するよくある質問に対して回答します。社会福祉士を目指すべきかお悩みの方はぜひご覧ください。
社会福祉士にしかできないことは何ですか?
社会福祉士にしかできないことは、利用者さんが抱えている経済的・身体的・社会的な問題の背景を深く考察し、将来を見据えた支援をすることです。問題の根本原因を探るだけでなく、現在抱えている問題の再発防止までを視野に入れた支援を提供できるのは、社会福祉士ならではといえるでしょう。
医療ソーシャルワーカーのやりがいとは?
医療ソーシャルワーカーのやりがいは、利用可能な支援制度やサービスの紹介を通して、患者さまやご家族から感謝されることでしょう。医療ソーシャルワーカーとは、病院の病棟やクリニックで患者さんやご家族への相談や支援を行う仕事です。入院中の医療費の支払い、治療しながらの職場復帰など、心理面や経済面などで不安を抱える方をサポートできる達成感を得られるでしょう。
社会福祉士のメリットとデメリットは何ですか?
社会福祉士として働くメリットには、「感謝の言葉が貰える」「幅広い業界で活躍できる」「将来性があり需要が高い」などがあります。人によっては、相談・調整業務による対人ストレスや、業務範囲の広さ、成果の見えにくさなどにデメリットを感じることもあるようです。
まとめ
社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉法」に基づく国家資格である「社会福祉士」を取得している人のことです。相談・援助・調整業務を行い、相談者の身体や精神、経済にまつわる問題を解決します。無資格でも相談業務に携われる場合もありますが、社会福祉士と名乗るには資格の取得が必須です。
社会福祉士のやりがいには、「利用者さんやご家族から感謝される」「地域課題を解決に導ける」「チームで一体となって支援できる」などが挙げられます。そのほか、「専門知識やコミュニケーション能力を活かして働ける」「人材を育てる経験ができる」といった魅力も。「幅広い分野で活躍できる」「社会的需要が高く将来性がある」「自身の成長を実感できる」といった点も、働くうえでのやりがいといえます。
社会福祉士としてやりがいを感じながら長く働くなら、キャリアアップや仕事の形態を変えることを検討してみましょう。「社会福祉士の上位資格を取得する」「成年後見人として活動する」「開業して社会福祉士事務所を経営する」などの道を選ぶ方法もあります。
社会福祉士として働きたい方は、介護福祉業界専門の転職エージェント「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)では、職場の雰囲気や給料など、応募先のリアルな情報をお伝えできます。キャリアアドバイザーが事業所に直接ヒアリングして情報を集めているため、希望条件に合った求人を紹介可能です。社会福祉士の仕事にチャレンジしたい方は、この機会にぜひご相談ください。
内定後まで安心サポート
 生活相談員の求人一覧はこちら
生活相談員の求人一覧はこちら