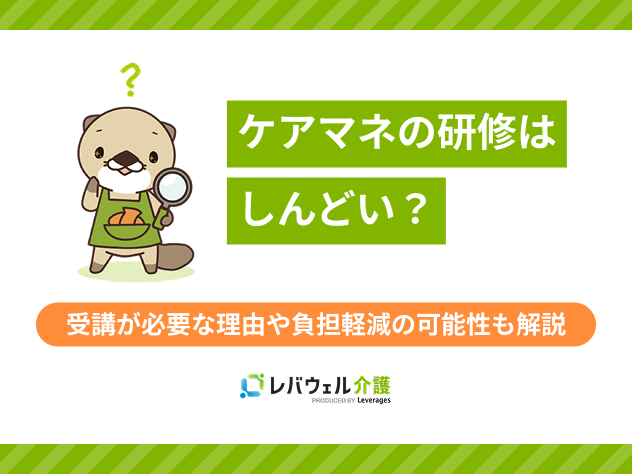
この記事のまとめ
- ケアマネの研修がしんどい理由は、仕事との両立や費用負担が大変だから
- 介護支援に必要な知識と技術を維持するために、ケアマネの研修が実施される
- ケアマネの研修は受講者の負担が大きいため、見直しが検討されている
「ケアマネの研修がしんどいと言われる理由は?」と気になる方もいるかもしれません。ケアマネの研修は長時間で、提出課題に対応する必要もあることから、「仕事と研修の両立がしんどい」と感じる方もいるようです。この記事では、ケアマネの研修がしんどいと言われる理由や必要性を解説。研修を乗り越える方法や、今後の負担軽減の可能性についてもまとめました。ケアマネの研修を受講する予定がある方は、ぜひご覧ください。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!ケアマネの研修は「実務研修」「更新研修」の2種類
ケアマネジャー(介護支援専門員)の研修には、「実務研修」と「更新研修」の2種類があります。実務研修は、ケアマネジャー試験に合格した後に受講する研修で、正式名称は「介護支援専門員実務研修」です。試験に合格しても、実務研修を受けないとケアマネジャーとして働けません。
更新研修とは、ケアマネジャーの資格を更新するために受講する研修です。「介護支援専門員証」の有効期限は5年間で、有効期間の満了日までに更新研修を修了しなければケアマネジャーとして働けなくなってしまいます。万が一、有効期間を過ぎてしまった場合は、再研修を受講したうえで新たに交付申請を行わなければいけません。
今の職場に満足していますか?
▼関連記事
ケアマネ更新研修は廃止される?現状と問題点、見直しの動きを解説
「ケアマネの研修はしんどい」と言われる理由
ケアマネジャーの法定研修は、受講時間が長かったり、課題の提出が必要だったりすることから、「仕事と研修の両立が大変でしんどい…」と感じる方がいるようです。ここでは、ケアマネジャーの研修がしんどい理由を解説します。
長時間の研修を受講しないといけない
ケアマネジャーの研修は長時間のため、受講が負担でしんどいと感じることがあります。実務研修のカリキュラム時間は87時間、更新研修は32~88時間。研修時間の長さに伴って必要な期間も長くなるため、計画的な受講が必要です。
仕事や家庭の事情でスケジュールどおりに受講が進まない場合があり、大変さにつながってしまうようです。
研修費用の負担がある
費用負担があることも、ケアマネジャーの研修をしんどいと感じる理由の一つです。以下で東京都の受講費用を紹介するので、一例として確認してみましょう。
| 研修内容 | 受講費用 |
| 実務研修 | 4万4,600円 |
| 専門研修I | 3万4,500円 |
| 更新研修(88時間) | 5万8,300円 |
| 更新研修(32時間) | 2万3,800円 |
| 更新研修(54時間) | 2万8,500円 |
| 再研修 | 2万8,500円 |
参考:東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト:東京都介護支援専門員研修について「第27回第1期実務研修(p.2)」「令和6年度第3期専門研修I(p.3)」「令和6年度第2期更新研修88時間(p.2)」「令和6年度第3期32時間(p.3)」「令和6年度第3期更新研修(実務未経験者)(p.2)」「令和6年度第3期再研修(p.2)」
上記の受講料のほか、研修会場に向かう際の交通費なども必要です。各都道府県の受講費用は、実施団体のWebサイトなどでご確認ください。
出典
東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト「研修」(2025年4月4日)
課題やグループディスカッションが大変
研修に参加するだけではなく課題の提出が必要なことも、受講者の負担になっています。学習の理解度を把握することを目的に、レポートの提出が複数回求められるため、働きながら課題をこなすことをしんどいと感じる方がいるようです。
研修では、学習内容の理解を深めるためのグループディスカッションが実施されます。面識のない人と話し合ったり、課題を一緒にこなしたりするのに苦労することもあるでしょう。
日程調整・研修会場への移動の手間がかかる
働きながら研修に参加する場合は日程調整が必要なため、スケジュール管理を大変に感じることも。ケアマネジャーの研修は、実施団体が決めた日程スケジュール・指定会場での受講が求められます。研修日に合わせて勤務日を調整しなくてはいけない場合、勤務先への相談が必要です。
また、東京都のようにオンラインの講義を導入する自治体がある一方で、すべての科目で通学が必要な自治体もあります。会場によっては移動に手間がかかり、「電車の乗り継ぎが大変」「移動時間が長い」などの理由で疲れてしまう方もいるでしょう。
【体験談】実務研修を受講した先輩ケアマネの声
レバウェル介護(旧 きらケア)では、実務研修を受講しケアマネジャー274人を対象に、「実務研修って大変?」というアンケートを実施しました(2025年2月28日)。「大変だった…」は74%、「余裕だった!」は26%という結果から、実務研修を大変に感じる方が多いことが分かります。
先輩ケアマネの実務研修の感想は、以下のとおりです。
- 仕事と研修と課題提出をこなすのが大変
- 拘束される時間が長い
- 基本的に休めない
- シフトを調整してもらうので職場に申し訳ない
- 経管栄養の勉強や医療的ケアの実技が大変
- 正解が分からないなかで課題が多い
- グループワークが大変
- 予定を立てにくい
仕事と研修受講を両立する必要があるため、スケジュールを調整するのが大変だと感じることがあるようです。また、多くの課題に対応しなくてはならない難しさもあります。ケアマネジャーの研修は働きながら受講する人が多いので、しんどいと感じないためには、休みの調整や学習サポートといった職場の協力が重要です。
ケアマネの法定研修が必要な理由
ケアマネジャーの法定研修は、介護支援に関する専門的な知識・技術を向上させ、利用者さんに対して適切なケアマネジメントを行うことを目的に実施されます。
一人ひとりの利用者さんが、必要なサポートを必要な分だけ利用できるよう調整するのが、ケアマネジャーの役割です。介護保険制度の改正に合わせて知識をアップデートしたり、実習を通して技術を磨いたりなど、高水準の知識や技術を学ぶ機会として法定研修が行われています。
▼関連記事
ケアマネジャーに必要な知識は?役割や求められるスキルを解説
ケアマネの実務研修の概要
ここでは、介護支援専門員実務研修の概要をまとめました。東京都を例に挙げて紹介するので、実務研修を受ける方は参考にしてみてください。
研修日程
東京都の介護支援専門員実務研修の日程は前期・実習・後期の3段階に分かれており、約3ヶ月にわたって履修します。都道府県によって日程スケジュールは異なり、年間を通して複数回実施するところもあるようです。
研修場所
東京都でケアマネジャー試験を受験した方は、東京都での受講が原則です。実務研修は、基本的に試験を受けた都道府県で受講します。ただし、引っ越しなどのやむを得ない事情により、登録先の都道府県で受けられない場合は、ほかの都道府県でも受講できるようです。
研修内容
実務研修は、87時間の講義・演習と、原則3日間の実習で構成されます。なお、標準的な研修内容は国が定める基準に基づいて構成されるため、全国共通です。
前期課程
前期課程は受講期間が1ヶ月程度です。ケアマネジメントの役割や基本的な考え方から、ケアマネジャーに関連する法令などの基本知識、他業種との連携の仕方まで幅広く学びます。
実習
前期課程を修了後、実施団体が指定する居宅介護事業所で3日間の実習が行われます。実際の事例への対応を通して、アセスメントシートの作成、利用者のニーズに合わせたケアプランの作成、モニタリング、チームマネジメントを含む業務の流れを掴むことが可能です。
後期課程
後期課程は受講期間が2ヶ月程度で、講義動画の視聴とグループワークが行われます。前期課程や実習で学んだことをベースに、さらに実践的なスキルを身につけられるでしょう。
実習で学んだことの共有や課題点の振り返りなどを実施します。脳血管疾患、認知症、心疾患など、利用者さんの具体的な疾患を想定し、アセスメントの方法や課題分析の視点、留意点などを学ぶ内容です。
ケアマネの更新研修の概要
ここでは、更新研修の概要を紹介します。実務経験の有無や更新研修の受講回数、資格の適用状況によって受ける更新研修の種類は異なるので、以下で確認してみましょう。
研修時期
ケアマネジャーの更新研修は、基本的に介護支援専門員証の有効期限の1年前から受けられます。有効期限が切れる間近に受講を検討するのではなく、早めに受講スケジュールを立てるようにしましょう。
研修が1年間に複数回行われる自治体では受講者が分散されますが、開催数が限られていると定員オーバーの可能性があります。
研修場所
実務研修と同様に更新研修も、ケアマネジャーとして登録している都道府県での受講が基本です。Webサイトに掲載されている過去の研修情報を参考にすると、研修準備をスムーズに進められます。
なお、引っ越しや定員オーバーなどの事情により、登録先以外の自治体での受講を希望する場合は、登録先・受講希望先の都道府県の両方への相談が必要です。
近年、オンライン受講を取り入れる動きがあり、講義にオンライン配信を採用している自治体も少なくありません。演習や実習は、指定の機関で実施される場合が多いでしょう。
状況別の受講すべき研修
以下では、ケアマネジャーの状況別に受講すべき研修をまとめています。
1回目の更新で6ヶ月以上実務に従事している場合
1回目の更新で、ケアマネジャーとして働いて6ヶ月以上の方は、まず「専門研修I」を受講しましょう。専門研修Iは、資格証の更新期限の1年以上前でも受講可能です。
専門研修Iの受講後は、就業から3年以上経過していれば、「専門研修II(32時間)」を受講します。実務経験が3年に満たなければ、「更新研修(32時間)」を受けて介護支援専門員証を更新しましょう。
1回目の更新で実務に従事して6ヶ月未満の場合
1回目の更新で、ケアマネジャーとして就業してから6ヶ月未満の方は、「更新研修(88時間)」を受講します。また、ケアマネジャーとして就業していたものの、現在は従事していない方も、88時間の更新研修の受講対象者です。
介護支援専門員証の交付後に実務経験がない場合
ケアマネジャーの資格を取得・登録してから実務経験がない方は、「更新研修(54時間)」を受講して資格を更新します。
なお、更新研修(54時間)受講後も実務経験がないまま5年が経過してしまうと、再び更新研修(54時間)を受ける必要があるので注意しましょう。
過去に計88時間の更新研修を修了した実務経験者の場合
2回目以降の更新で、過去に計88時間の更新研修を受けたことがある方は、「専門研修II」もしくは「更新研修(32時間)」を受講します。ともに32時間の研修です。
過去に計88時間の更新研修を受けていない実務経験者の場合
2回目以降の更新で、過去に計88時間の更新研修を受けていない実務経験者は、「専門研修I+専門研修II」「専門研修I+更新研修(32時間)」「更新研修(88時間)」のいずれかを受講します。どのパターンでも、受講時間は合計88時間です。
介護支援専門員証の交付を受けず5年経過している場合
ケアマネジャーとして登録後に介護支援専門員証の交付申請をしないまま5年以上経過した方は、「再研修(54時間)」を受けます。また、介護支援専門員証の有効期間が過ぎていて再交付を希望する方も、54時間の再研修を受講しなければいけません。
▼関連記事
ケアマネ資格を更新しないとどうなる?必要な手続きや研修、失効時の対処法
研修内容
更新研修は、講義やグループ演習、実習で構成されます。ケアマネジメントの基本を学ぶ・振り返りをする・事例検討を行うなど、研修ごとに受講対象者の経験に応じた学習内容になっているのが特徴です。
専門研修I
専門研修Iは、合計56時間の研修です。これまでの自身のケアマネジメントを振り返り、ケアマネジャーとして解決していくべき課題を設定します。
そのほか、相談援助に必要な知識・技術や、他職種連携の実践なども学習内容です。利用者さんの疾患やニーズに応じたケアプランを作成できるよう、ケアマネジメントの演習も行います。
専門研修II
専門研修IIは、合計32時間の研修です。定期的に改正される介護保険制度を学んで知識をアップデートしたり、福祉用具の活用方法を確認したりして、利用者さんに適切なケアを提案できるよう学び直します。
また、地域包括ケアシステムにおいてケアマネジャーが担う役割や、ケアマネジメントの実践事例の研究・発表なども学習内容です。
再研修
再研修では、実務経験がないことを考慮して、チームケア・地域包括ケアシステムの重要性や、ケアマネジャーの業務に関連する法令・規定についての講義が実施されます。また、高齢者に多い疾患に関する講義があったり、サービス担当者会議の演習があったりするのも特徴です。
更新研修
更新研修は3種類あり、いずれも専門研修や再研修と同等のカリキュラムです。「更新研修(32時間)」は、専門研修IIに相当し、「更新研修(88時間)」は専門研修I・IIに相当。「更新研修(54時間)」は、再研修に相当する内容です。
出典
東京都福祉保健財団ケアマネジャー専用サイト「研修」(2025年4月4日)
ケアマネのしんどい研修を乗り越える方法
レバウェル介護(旧 きらケア)のアンケートで、ケアマネジャーに「研修を乗り越えるためのアドバイス」を尋ねたところ、以下のような回答がありました(2025年3月1日)。
- グループワークで一緒に頑張れる仲間を見つける
- 今後の人脈づくりに役立つと考えて前向きに参加する
- 面白いと感じるポイントを見つける
- やるべきことを後回しにしないようにする
研修を乗り越える方法として、「仲間を見つけることが大切」という意見が寄せられました。グループワークやグループディスカッションなど、研修に参加している人と関わる機会が多いため、励まし合うことはモチベーションを保つのに有効です。
また、課題を計画的に進め、スケジュールに余裕を持たせるように心掛けると、仕事と研修を両立させられるでしょう。
2024年4月からの研修カリキュラムの変更点
2024年4月に、ケアマネジャーの法定研修のカリキュラムが一部変更されました。以下で変更点を確認してみましょう。なお、科目の時間配分が調整されたため、カリキュラム全体の時間数そのものは変わっていません。
「適切なケアマネジメント手法」などの導入
根拠ある支援を実施できるよう、「適切なケアマネジメント手法」がカリキュラムに盛り込まれました。適切なケアマネジメント手法とは、ケアマネジャーが培ってきた知見で共通する部分を体系化したものです。研修では、個別ケースを想定し、情報を収集・分析。実際にケアプランを立案するなかで、効果的なマネジメントを行うスキルを養います。
また、「科学的介護(LIFE)」も各科目類型に追加されました。科学的介護(LIFE)は、ケアプランや介護計画書などのデータを一元的に管理・分析し、その情報をフィードバックするシステムです。フィードバックされた情報を利用者さんのケアプランに反映することで、質の高い支援を行うことが期待されています。
出典
厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」(2025年4月4日)
現代の社会動向の反映
社会情勢の変化に応じて、近年の社会動向や課題がカリキュラム内容に反映されています。たとえば、ヤングケアラーの問題や、仕事と介護の両立支援の必要性などを追加。介護を必要とする方だけではなく、そのご家族の方にも配慮できるプランニング力を養成します。
また、認知症を患う方や終末期ケアが必要な方が増えることで、意思決定支援の需要が見込まれるため、職業倫理に関する受講時間を増やして理解促進を試みている点も特徴です。
出典
厚生労働省「介護支援専門員資質向上事業」(2025年4月4日)
ケアマネ研修は今後どうなる?負担軽減の可能性は?
厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」によると、ケアマネジャーの人材を確保するために、法定研修の見直しが検討されているようです。
具体的には、更新研修の受講時間を減らすのが適当ではないかという意見があります。また、「全国一律で実施する講義にオンライン受講を導入する」「都道府県が独自の科目を設ける場合に負担が増えないような仕組みづくりをする」などの負担軽減策も検討中のようです。
ケアマネジャーの質を維持することを前提にしつつ、より長く活躍できるよう、受講者の負担軽減について話し合われています。
出典
厚生労働省「第116回社会保障審議会介護保険部会の資料について」(2025年4月4日)
▼関連記事
ケアマネは今後どうなる?AIの活用で不要になるの?将来性や需要を解説!
ケアマネの研修に関するよくある質問
ここでは、ケアマネの研修についてよくある質問にお答えします。実務研修に合否があるかどうかや、更新研修の廃止の可能性などが気になる方はチェックしてみてください。
ケアマネの実務研修に落ちることはありますか?
実務研修中に求められる課題は認定調査とケアプランの作成が主で、フローに従って対応し提出すれば、落ちる可能性は低いでしょう。ただし、必要な提出物が欠けるなどの不備があると、落ちてしまう場合があるようです。
ケアマネの更新研修は廃止されますか?
2025年4月現在、ケアマネの更新研修が廃止される予定はありません。ただし、現在の研修制度は受講者にとって経済的・時間的な負担が大きいことから、研修内容の見直しが検討されています。検討内容の詳細は「ケアマネ研修は今後どうなる?負担軽減の可能性は?」の見出しで解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
ケアマネの実務研修を仕事しながらこなすには?
ケアマネの実務研修を働きながらこなすには、計画的に課題を進めることと、仕事のスケジュール調整をすることが必要です。「仕事で疲れているから」と後回しにしていると、提出期限に追われてしまう可能性があるため、事前にスケジュールを立てて課題をこなしましょう。また、研修の全日程に参加できるよう、上司に相談しておくことも大切です。「ケアマネのしんどい研修を乗り超える方法」の項目でも解説しているので、あわせてご一読ください。
ケアマネの実務研修を受けないとどうなるの?
ケアマネジャー試験に合格しても、介護支援専門員実務研修を受けなければ、ケアマネとして働けません。実務研修では、ケアマネとして働くために必要な専門的知識・技能を身につけることが可能です。「ケアマネの実務研修の概要」の見出しでは実務研修について解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
まとめ
ケアマネジャーの研修は、提出課題が多いことや、仕事と研修の両立が大変なことから、「しんどい」と感じる場合があります。また、研修費用の負担があることも、大変に感じる要因になっているようです。
介護サービスを必要とする方が適切なサポートを受けるには、一人ひとりの状態に応じたケアプランの作成が必要不可欠。ケアマネは、5年ごとに研修を受講して、常に高水準の知識や技術を身につけることが求められます。
ケアマネの研修を乗り越えるには、仲間を見つけることや、計画的に課題をこなすことが大切です。仲間と励まし合うことで、モチベーションを保ちやすくなります。また、事前にしっかりスケジュールを立てれば、課題の提出に追われることなく、仕事と研修を両立させられるでしょう。
現状の研修制度は受講者にとって経済的・時間的負担が大きいため、研修内容の見直しが検討されています。今後も介護需要は増加傾向にあるため、ケアマネの質・量をともに確保できるよう、負担軽減に向けた取り組みが行われるかもしれません。
「研修費用の負担がきつい」「研修がある日は仕事を休まないといけない」とお悩みの方は、レバウェル介護(旧 きらケア)を利用してみませんか?レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェント。豊富な介護求人のなかから、研修費用を負担してくれる職場や、研修日を出勤扱いにしてくれる職場を紹介できます。
また、専任のキャリアアドバイザーがキャリア相談に応じているため、ケアマネ以外の働き方など多様な提案が可能です。サービスの利用はすべて無料なので、まずは気軽にお問い合わせください。
今の職場に満足していますか?
 ケアマネージャーの求人はこちら
ケアマネージャーの求人はこちら