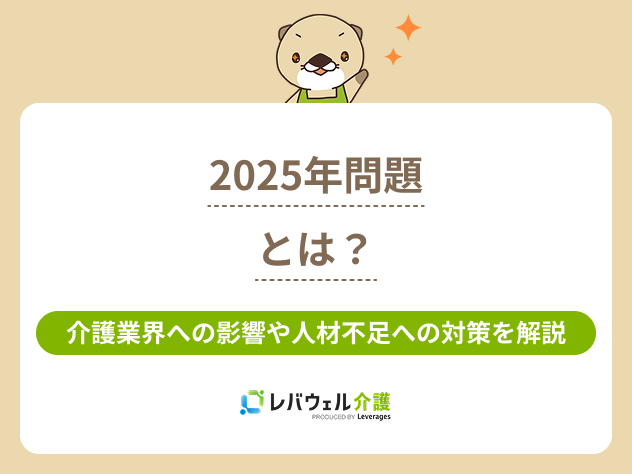
この記事のまとめ
- 2025年問題とは、後期高齢者が急増することで社会問題が生じること
- 2025年問題により、介護業界では人材不足が深刻化するなどの課題がある
- 介護の2025年問題に対応するため、国は人材確保・育成に取り組んでいる
「2025年問題」が介護業界に及ぼす影響について気になる方もいるのではないでしょうか。2025年問題は、後期高齢者が急増することにより生じる社会問題のことで、介護業界は深刻な人材不足に陥ると懸念されています。この記事では、2025年問題の概要や、介護業界で起こる問題を解説。2025年問題に対する国の取り組みや、私たちにできることも紹介します。2025年問題に興味がある方は、ぜひご一読ください。
「2025年問題」とは?
2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることにより、さまざまな問題が生じることです。現役世代の割合が下がり、さまざまな産業で労働力不足に陥るとの予測。特に、医療・介護業界の人材不足が加速することや、社会保障制度の維持が難しくなることが懸念されています。
厚生労働省の「今後の高齢者人口の見通しについて」によると、2025年には後期高齢者の人口が2,179万人に達し、全人口の約18%を占める見込みです。
出典
厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」(2025年3月7日)
登録は1分で終わります!
「2025年問題」の先に「2040年問題」がある
介護業界には、2025年問題だけではなく、「2040年問題」もあります。2040年問題とは、2040年ごろに65歳以上の高齢者人口がさらに増加し、介護業界の人材不足が2025年以上に顕著になると考えられていることです。
厚生労働省の「我が国の人口について」によると、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%を占めると推計されています。2040年には、団塊世代の子ども(団塊ジュニア世代)である1971~1974年生まれの人が65歳を迎えるため、介護需要が増加する見込みです。
また、同省の「今後の高齢者人口の見通しについて」によると、2042年には65歳以上の人口が3,878万人になりピークを迎える予測。現役世代が働きながら介護をする状況が生まれ、生産性の低下や介護による離職が起こり、社会全体に大きく影響することが懸念されています。
出典
厚生労働省「我が国の人口について」(2025年3月7日)
厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」(2025年3月7日)
介護業界における「2025年問題」
「2025年問題」が介護業界に及ぼす影響として、以下の点が懸念されています。
- 介護人材の不足により、サービス提供能力の低下や施設の利用制限につながる可能性がある
- 社会保障費が膨大になり、社会保障制度を維持できない可能性がある
- 現役世代の介護参加が求められることで、就業・就職を断念せざるを得ない状況が生じる可能性がある
ここでは、「人材不足」「介護サービスの縮小」「介護難民の増加」「ビジネスケアラーの増加」の項目に分けて、介護業界の2025年問題について解説します。
深刻な人材不足
2025年問題により、介護業界の人材不足が深刻になることが指摘されています。厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、介護サービスの利用数から推計した、2026年度に必要な介護職員は約240万人です。2022年度の介護職員は約215万人のため、2026年度の必要数に対して約25万人不足していることが分かります。
また、2040年度に必要な介護職員は約272万人です。2022年度からの18年間で約57万人の介護職員を増員しなければならない計算のため、人材不足はより深刻になっていく可能性があります。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(2025年3月7日)
▼関連記事
介護業界の人材不足はなぜ起こる?原因や対策をわかりやすく解説
介護サービスの縮小
2025年問題は、介護サービスの縮小に影響する可能性があります。介護保険を利用して介護サービスを利用する高齢者が増えると、社会保障費が増加。現役世代の割合が減り税収が減少することで、社会保障費をまかなえなくなる可能性があります。その結果、介護サービスの提供範囲や内容を見直しせざるを得ない状況が生じるかもしれません。
介護難民の増加
人材不足や介護サービスの見直しにより、必要な支援を受けられない「介護難民」が増加する可能性があります。たとえば、介護の優先度が低いと判断され、要介護度が低い方の介護サービスの利用は後回しにされたり、要介護認定の基準そのものが厳しくなったりすることが考えられるでしょう。
厚生労働省の「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」によると、2022年度の特別養護老人ホームの入所申込者のうち、約23万人の方が入所待ちの状況です。今後、介護サービスの利用条件が厳選されることで、介護難民がより増えてしまうかもしれません。
出典
厚生労働省「第105回社会保障審議会介護保険部会」(2025年3月7日)
▼関連記事
介護難民とは?原因や解決策などの現状と介護人材の今後について解説!
ビジネスケアラーの増加
2025年問題により高齢者や介護難民が増えることで、ビジネスケアラーの数が増加する見込みです。ビジネスケアラーとは、働きながら介護をする人を指し、ワーキングケアラーとも呼ばれます。
経済産業省の「介護政策」によると、2020年に262万人だったビジネスケアラーが、2025年には307万人に増加。2030年のピーク時には318万人になると推計されています。また、介護離職者の数も、2025年以降、毎年10万人程度が見込まれているようです。
介護と仕事を両立できなくなると、介護離職せざるを得なくなり、キャリアへの影響や収入減による貧困が懸念されます。
出典
経済産業省「介護政策」(2025年3月7日)
介護業界の「2025年問題」に向けた対策
介護業界の「2025年問題」に対応するためには、それぞれの問題に応じた対策を取ることが重要です。また、介護業界に人材が定着するよう、処遇や職場環境、業務内容の改善にも取り組む必要があるでしょう。
ここでは、「人材確保・育成」「労働条件の改善」「職場環境の改善」「AIの活用」「地域包括ケアシステム」「ビジネスケアラー対策」について、国の取り組みを中心に解説します。
人材確保・育成
介護の担い手不足を解消するために、国では人材確保・育成の取り組みを進めています。厚生労働省の「介護人材確保に向けた取組」によると、介護業界で働いたことがない人向けに、介護に関する入門的研修の実施を推進。入門的研修では介護の基礎知識を学べるので、入職後の介護現場で役立てられたり、転職時のミスマッチを防げたりするでしょう。
また、人材確保の取り組みとして、人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度も事業化されています。厚生労働省の「人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度の実施について(p.3)」によると、「労働環境、処遇の改善」「新規採用者の育成体制」「キャリアパスと人材育成」などの項目に設けて事業所を評価し、人材育成に対する事業所の取り組みを可視化。介護業界で就職・転職先を選ぶ際は、認証の有無を一つの目安にできるでしょう。
出典
厚生労働省「介護人材確保に向けた取組」(2025年3月7日)
厚生労働省「人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度の実施について」(2025年3月7日)
労働条件の改善
介護業界の人材不足を解消するためには、介護職の労働条件を改善することが必要です。労働条件の改善に向けた動きとして、国は、2024年に「介護報酬改定による賃上げ」「介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策」などに取り組みました。
厚生労働省の「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」によると、2024年度に処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引き上げを実施。2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップにつながるよう制度の見直しに取り組みました。
また、同省の「令和6年度補正予算案の主要施策集(p.7)」によると、「介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策」として806億円の補正予算を計上。介護職の給料アップや職場環境の改善などが期待されます。
処遇改善については「【2025年最新】介護職員の給料は上がる?処遇改善の取り組みを解説」の記事で解説しているので、あわせてご一読ください。
出典
厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月7日)
業務効率や職場環境の改善
人材不足のなかで介護需要に対応するには、介護職員の業務負担を軽減したり、働きやすい環境を整備したりすることも重要です。
厚生労働省の「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 改訂版(p.8)」では、以下の「介護サービスにおける生産性向上のための7つの取組」が業務の効率化に有効だと示されています。
- 職場環境の整備
- 業務の明確化と役割分担
- 手順書の作成
- 記録・報告様式の工夫
- 情報共有の工夫
- OJTの仕組みづくり
- 理念・行動指針の徹底
たとえば、「職場環境の整備」では、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)に基づき、不要なものを処分したり、動線を考慮して棚を配置したりして、安全かつ機能的なレイアウトに変更します。
「手順書の作成」では、職員の知識やノウハウを書き出したり、業務ごとに要する時間を抽出したりして問題点を把握。職員の業務の質を画一化し、時間配分を明確にすることで業務効率化を図ります。
介護施設・事業所ごとに解決すべき課題は異なるため、国や自治体のガイドラインを参考にしつつ、職場環境の改善に向けて職員同士で話し合うことも重要です。
出典
厚生労働省「介護分野の生産性向上 ~お知らせ~」(2025年3月7日)
AI活用による生産性の向上
今ある人材で最大限の効果を生むために、AIを活用して作業を効率化する取り組みも実施されています。
厚生労働省の「介護分野におけるAI等の活用状況(p.5)」によると、介護職員の負担軽減を目的に、2022年度に地域医療介護総合確保基金137.4億円を活用。介護ロボット、見守りセンサーなどを導入して介護施設・事業所の生産性向上を図りました。
また、介護ICTを活用した、介護現場の業務効率化も試みています。たとえば、介護ソフト・アプリを活用すると、介護記録の手間を減らせたり、事務処理の業務を一本化できたりするため、日々の業務負担の軽減につなげることが可能です。
出典
厚生労働省「第15回保健医療分野AI開発加速コンソーシアム資料」(2025年3月7日)
▼関連記事
進化する介護業界!現場の負担軽減と業務効率化をIT技術で実現する企業
介護ロボットとは?現場の介護職員や利用者さんに与える影響について解説!
地域包括ケアシステムの構築
国は、2025年問題に対応するために「地域包括ケアシステム」を構築し、地域全体で高齢者の方を支えていくことを目指しています。地域包括ケアシステムとは、住まい・医療・介護・介護予防・支援活動を地域で包括的に提供することです。
要介護度が上がっても、高齢者の方にはできる限り住み慣れた地域・自宅で過ごしてもらえるようにサポート。介護が必要なときは介護サービスを、体調が悪いときは医療サービスを迅速に受けられる体制を構築しています。
また、医療と介護の連携も、地域包括ケアシステムの大きな目標です。自宅にいながら医療と介護を包括的に受けられるようにすることで、高齢者の方が最期まで自分らしい暮らしを送れるように支援します。
出典
厚生労働省「地域包括ケアシステム」(2025年3月7日)
ビジネスケアラー対策
厚生労働省の「介護休業制度」によると、育児・介護休業法の改正を実施。2025年4月1日から、介護をすると申し出た職員に対して、介護休業・両立支援制度を個別に周知することや、雇用環境を整備することが事業主の義務となりました。
介護休業を利用すると、対象家族1人につき3回、通算93日まで休業することが可能です。家族の介護が必要になったとしても、職場の理解を得て柔軟な働き方ができれば、介護と仕事を両立させやすくなるでしょう。
出典
厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~」(2025年3月7日)
▼関連記事
介護離職ゼロに向けた政府の取り組みとは?介護職不足の現状についても解説
「2025年問題」に向けて私たちができること
2025年問題に対応するには国や自治体が率先して取り組む必要がありますが、私たちも「何かできることはないか」と考えることが大切です。地域包括ケアシステムでは、行政が行うサービス以外にも、NPOやボランティア、民間企業などの協力が必要不可欠となっています。
身近な取り組みとして、病気にならないように生活習慣の改善を心掛けることは、介護予防につながるでしょう。介護需要を増加させないためには、要介護状態にならないように健康寿命を延ばすことが重要です。また、認知症に関する理解を深めたり、介護の資格を取得したりすれば、家族の介護や地域住民の支援に役立てられます。
2025年問題は、誰にとっても無関係なことではありません。介護予防について調べるなど、できることから始めておくことで、自分や身近な人が年を重ねることへの不安を軽減できるでしょう。
介護職は安定的に働ける需要の高い職種!
人材不足の状況にある介護業界では、今後も引き続き介護職の需要が高く、安定的に働けます。たとえば、ライフイベントにより引っ越しが必要になった場合も、介護職なら全国どこでも仕事があるため、キャリアを途切れさせず働ける可能性が高いでしょう。
介護職は利用者さんやご家族との直接的な関わりが多い仕事なので、「ありがとう」と感謝の言葉をもらえることも。誰かの役に立っていることを実感できる、やりがいのある仕事です。また、人材確保が課題である介護業界では、今後も労働条件の改善が期待できます。
「待遇面が不安だったけど、少し興味が出た」「働くなら安定的に働きたい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)に問い合わせてみませんか?レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェント。豊富な介護求人のなかから、「未経験可」「高給与」の求人や「資格取得支援」がある職場をご紹介できます。
▼関連記事
介護職の仕事内容とは?資格は必要?やりがいやメリットもご紹介
介護業界の「2025年問題」に関するよくある質問
ここでは、介護業界の「2025年問題」についてよくある質問にお答えします。介護職の給料がどうなるのかや、2040年問題との違いが気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
「2025年問題」で介護職員の給料はどうなるの?
2025年問題による人手不足を解消する目的もあり、国を挙げて介護職員の給料を改善してきました。2024年の介護報酬改定では、処遇改善加算の制度が見直され、加算率の引き上げが行われました。今後も人材を確保する必要があるため、介護職の待遇改善は継続され、給料が上がる可能性があるでしょう。詳細はこの記事の「労働条件の改善」で解説しているので、気になる方はぜひご一読ください。
介護業界の2025年問題と2040年問題の違いは?
2025年問題は、団塊の世代が75歳以上になり、後期高齢者が顕著に増加すること。一方の2040年問題は、団塊の世代の子どもが65歳以上になり、高齢者人口が増加することです。2025年が人口構造の転換期で、2040年が高齢者人口のピークといえます。詳しくは、「「2025年問題」の先に「2040年問題」がある」で解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
75歳以上の後期高齢者が増加し、「2025年問題」に直面する日本では、介護業界の人材不足や介護サービスの縮小、介護難民の増加などが課題です。国や自治体では、人材確保・育成、労働条件の改善、業務効率化、職場環境の改善などを推進しています。さらに、地域包括ケアシステムを構築し、地域全体で高齢者の方を支える取り組みも実施中です。
「介護職に就いてやりがいのある仕事がしたい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)を利用してみませんか?レバウェル介護(旧 きらケア)のキャリアアドバイザーは介護業界に精通しているので、介護職が初めてという方も、働き方を相談しながら応募先を選べます。条件交渉や面接対策など、二人三脚で転職をサポート!サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にお問い合わせくださいね。
登録は1分で終わります!
 ヘルパー・介護職の求人はこちら
ヘルパー・介護職の求人はこちら